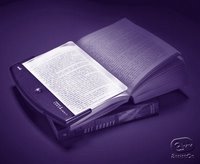良いデザインは模倣する
私は常々、そのあたりのことはもう少しおおらかに考えた方がいろんなことがうまく行くんじゃないかと考えていて、そんな内容の文章をここにも何度か書いたことがあるのですが、最近読んだ、ものつくりやデザインに関する有名な文章の中に同じような意味のことが書かれていて、うれしくなったのでご紹介します。
ここには、ものつくりやデザインの真理のようなものがとてもわかりやすくかかれています。そのなかに
良いデザインは模倣する。 模倣に対する態度はしばしば一巡する。初心者は知らず知らずのうちに模倣する。 そのうち、彼は意識的に独自性を出そうとする。 最後に、独自性よりも正しくあることがより重要だと気づく。 気づかずに模倣することは、ほぼ間違い無く悪いデザインをもたらす。 どこから自分のアイディアが来たのか知らない場合、 たぶんあなたは模倣者の模倣をしている。
というものがあります。世の中には模倣があふれていることがよく分かります。
何かと何かが似ていたとしても、全体としてそれぞれのオリジナリティがちゃんと保たれていて、それぞれの作者がお互いをちゃんと認め合っていれば、まわりがとやかく言う問題じゃないんだと思います。
[Design, Copyright]


















![Laundry [ランドリー] Laundry [ランドリー]](http://images.amazon.com/images/P/B00006C22B.09._SCMZZZZZZZ_.jpg)