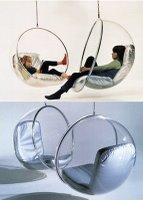建築設計に限らず、プロダクトデザインでもウェブでサインでもその類のものごとの場合、ある与条件に対する100パーセントの正解というのはありません。
建築設計でいえば、敷地やその周辺の環境・予算・必要機能などの諸条件によって解の方向性はある程度絞られはするものの、ただひとつの正解しかありえない状況にはなりません。そこにはいくつもの正解が存在し、そのどれもが100パーセントの正解ではありません。逆にいうと100パーセントの不正解もどこにも存在しません。
たとえば、子供がダンボールで作ったままごと用の家だって立派な建築だといえます。子供達はその家の中で無限の想像力をはたらかせて無限大の世界を創り出します。
「建築設計は住宅にはじまり住宅に終わる」と良くいわれます。私は大学を卒業してすぐに大きな設計事務所に勤めたので木造の個人住宅設計に携わることなく、鉄筋コンクリート造の巨大な建築物の設計ばかりをしてきました。それらは地方公共団体の発注による公共物件であったり、大きな企業の事務所ビルだったり、老人ホームだったりというものでした。
そんな仕事を10年続けてきて、だんだんとある疑問が生まれてきました。たとえば、老人ホームの設計であれば、一番に考えられるべきは、そこに居住するはずの老人達のことです。いかに居心地よく快適な空間を作るか、そこの居住するほかの老人達との自然なコミュニケイションを促し、良好なコミュニティをつくり出す手助けを出来るか、などということです。
しかし実際設計をするときに我々が接するのは、その施設を運営する人たちです。彼らから出てくる要望は、いかに老人を管理しやすくするか、外から見たときにいかに魅力的な施設に見えるか、いかに新規入居者を獲得するかということに主眼が置かれています。ごくまれに、老人達の居住性を第一に考える運営者もいますが、それは本当にひとにぎりの存在です。
事務所ビルをやっても、公共建築物をやっても、だいたい同じような類のことが起こりました。
その点、個人住宅の設計においては、ヒアリングをする人物と、文句を言ってくる人物と、実際にそこに居住する人物が完全に一致しています。規模は小さくても、その点でとてもやりがいのある仕事です。
設計者はみんな、建築設計に100パーセントの正解がないことを知りつつも、当然ながら、自分の提出した案が100パーセントの正解であるという勢いで施主に説明しなければなりません。施主を説得しなければ計画案が実施に至ることはないからです。
そのためには自分の案に100パーセントの自信を持っていなければなりません。その時、その不安定な自信を表面上揺るぎないものにするために必要になるのが、芸術性だとかセンスだとか呼ばれるものです。
どちらを選ぶか悩んだとき、もちろんさまざまな論理的な方法によって切捨てをして2案くらいに絞られたあと、最終的な判断の源は芸術性だとかセンスなのです。これは、設計者が施主に自分の案を説明するときにも同じで、最終的な自信の裏づけとなるのは自らのセンスだけなのです。
このセンスというのは、設計者の自己満足とかマスターベーションとかエゴなんて言葉で言い変えられるのかもしれません。その意味では、建築設計者はいつまでたっても、子供の頃にダンボールで作ったままごと遊びの家の中で無限の想像力を働かせて遊んでいるのかもしれません。
案外、最高の建築物はダンボールハウスなのかもしれません。
[
Architecture, Design]