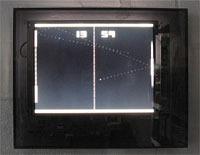たまにお店なんかでイライラしたお客さんが「俺は客だぞ。客をなんだと思ってんだ?!」などといったりしてるのを見ることがあります。私はあれ結構嫌いです。
日本ではどうも「客は偉い」とか「客はお店では威張っててもいい」とか思われているようですが、なぜでしょうか。三波春夫が「お客様は神様です。」と言ったからかどうなのかは分かりませんが。
私は基本的に、客が支払う料金は商品そのもの、サービス業においては基本的なサービスに対するものだと思っています。客は商品につけられた価格と同額のお金とその商品を交換します。タクシーでは目的の場所まで車に乗せてもらうこと、床屋では髪を切ってもらいシャンプーしてセットしてもらうという基本的なサービスに対して料金を支払います。どちらが偉くてどちらが従うということはなくて商品とお金、サービスとお金を交換しているにすぎません。
もちろんお店側は、また自分の店へ戻ってきてもらえるように、できるだけお客さんの気分が良くなるように笑顔で接したり、世間話をしたりします。でもそれはあくまでもプラスαのサービスであって、当たり前に行われるべきものではないのです。そのプラスαのサービスによってそのお店のグレードなどが決まってくるのは確かですが。
海外旅行へ行くといろんなところでチップを渡すことになります。最近はチップは要りませんってところも増えてきてはいるようですが。日本ではチップを渡す習慣がないので、なかなかうまく理解できない人も多いようです。
しかし、お店のレジで支払う料金はあくまでも商品そのものや基本的なサービスに対するもので、それ以上のサービスに対しては別に料金がかかると考えると、とたんに簡単に理解できるようになります。その別料金というのがチップなのです。
例えばレストランで、食事の後でお店に支払う料金は料理に対するものです。しかし食事中に気分よく過ごすための重要な要素は、食事の味や量だけではなくてサービスもあります。ウェイターやウェイトレスはお店からも給料をもらっていますが、これは食事を運んだり食事後の食器を運んだりという純粋な作業に対するものです。客が気分よく食事をするためのサービス、つまり、スマイルや軽いおしゃべり、最適なタイミングでの、あるいはお客の行動を先回りするような給仕などに対する対価は、ウェイターやウェイトレスが客から直接チップとしてもらうのです。
ですから、客はサービスを期待して、自分が気分よく過ごすために、ウェイターやウェイトレスにファーストコンタクトでチップを渡します。もう慣れている店で、顔見知りのウェイターが給仕についてくれた場合にはこれは要らないかもしれません。で、食事が終わったあとに、そのサービスに満足すればそれに見合った額をチップとしてテーブルに残します。満足できなければ置く必要はありません。最初にチップを渡したのに満足いくサービスがされなかったら、そのチップを返せということだってできます。これはちょっと勇気が要りますけどね。
難しいといわれるチップを渡すタイミングも、こうやって考えると分かりやすいはずです。
もちろんこれは西洋的な考え方ではあります。でも日本であっても、客とお店の基本的な関係は変わらないはずです。
長々といっぱい書いてきましたが、こんなことはどうでもよくって、ホントにいいたかったことは、お店でやたらと威張り散らしているお客さんは廻りをとても不愉快にさせるので、どうにかなって欲しいなぁってことなのです。
どうにかならないかな。
[Society]